
| ”地下室”という響きは、それだけで もう なんだか そわそわしてしまう。 わくわくでもなく、ドキドキでもなく そわそわするのは、 ”なにか、いつもと違うことがおこるかもしれない”と思うからだ。 |
| 例えば、安房直子著の『まほうをかけられた舌』(岩崎書店刊)。 腕の良いコックだった父を亡くした なまけ者の 若者が不思議な小人にであったところは地下の食 料品貯蔵庫。 そこで若者は小人のまほうで すばらしく上等の舌をもち 様々な店の看板料理を ぬすんで成功をおさめるのだが 何かが足りない。 |  |
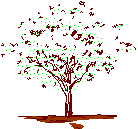 |
やっと若者が大切なのはオリジナリティなのだと気づいたところはやっぱり地下室だった。 そこからこの若いコックの 本当の第一歩が始まっていく。 |
| また 柏葉幸子著の『地下室からのふしぎな旅』(講 談社刊)では 地下室のかべが あちら側の世界との 境目になっていた。少女が 旅した もう一つの時間。 そこで出会ったもうひとり の自分自身。 つまり地下室は 私にとってそんなところ。 なんだか むしょうに明るい黄檗の地下室は あちらに世界への入り口というよりは あちらの世界からの入り口のようで あちら側の風に当たれば、どんなふしぎもおこりそう。こちらの世界で 何かいつもとちがうことを おこしてみたいと思ってしまう。 そんな地下室で いっしょに過ごして見ませんか? |
 |
|
|